こんにちは☆
シンプリストのちびかおです!
とってもお久しぶりのブログ更新なのですが…
今回はお知らせです!
先日発売されたサンキュ!9月号の、夏の断捨離特集コーナーに掲載していただきました!
実は2024年にSUUMOさんにオンライン取材していただいたのですが、その時は自分で撮影だったんですよね!
なので、マイホームでカメラマンさんが来ての撮影は初☆
なんと4ページも掲載してくださってます♪
ぜひお手に取っていただけると、サンキュ編集部さんも喜ぶと思います〜☆
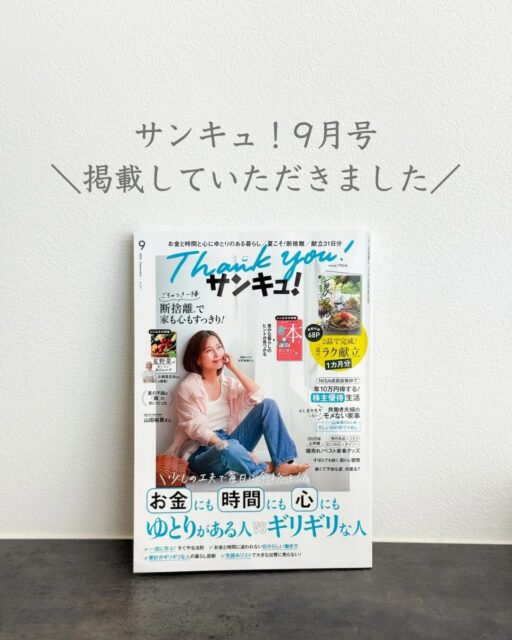
【掲載記念】特別企画!事前アンケート大公開☆
サンキュ!を購読してくださったフォロワーさんから、
「内容を読み込みます!」
「〜〜が参考になりました」
「考え方が勉強になります」
などと、感想をいただきました!
そこからヒントを得て、「事前アンケートの内容をシェアすれば、喜んでいただけるかも?」と考えたんですよね〜☆
なので、今回はアンケートの回答をブログでシェアしたいと思います♪
それぞれの内容に合わせて、もう少し深掘りした内容などを単体の記事にしたり、インスタ投稿にまとめてみようと思います〜!
とっても長いので、興味がある方だけどうぞ☆
Q1.以前は、掃除・片づけが苦手だったとのことですが、物を捨てようと思ったきっかけと、その時期を具体的に教えてください。
2013年、引っ越しの荷造りをしていた際に、義理の兄(引っ越し業者)から「めちゃくちゃ物が多いね」と言われたことがきっかけでした。
それまで自分では普通だと思っていた量が、他人の目には「多い」と映ったことに衝撃を受け、自分の暮らしを客観視できるようになったんです。
その後ネットサーフィンでたどり着いたインテリアブログから、「ミニマリスト」という概念に出会い、暮らしを整えることに強く興味を持ちました。
2015年からはメルカリを使い始め、不要な物を手放すことで収入も得られ、部屋もスッキリしていく心地よさを実感。
それ以来、「持つこと」に対する価値観が少しずつ変わっていきました。
メルカリやリサイクルショップで家のものを手放す時、大型の家具などは持ち込みも大変だったので、手放す時のことも考えた物選びをするようになりました。
Q2.片づかない部屋から、スッキリ・シンプルな暮らしへの変遷を、年ごとに具体的に教えてください。
- 2013年モノが多いと気付く
引っ越し準備中に義兄から「物が多い」と指摘され、初めて自分の暮らしを客観的に見直すきっかけに。
- 2014年捨て活に目覚める
インテリアブログや「ミニマリスト」の考え方に出会い、片付けや“捨て活”に目覚める。
- 2015年一気に手放す
物を減らすためにメルカリを活用。不要な物を手放しながら収入も得られ、「手放す=快適」という感覚が定着。大量のモノを一気に手放す。
- 2016年Instagramスタート
TVで取り上げられたことを機に、「なんでも捨てる」から「今の暮らしに合わせてアップデートする」へと価値観がシフトしていく。
- 2021年マイホームへ
注文住宅を建て、余白のある暮らしを実現。収納が最底辺でも5分で片付く家に!
Q3.いらない物を捨てて、良かったことをいくつでも具体的に教えてください。(心理的なことでもOK)
掃除が楽になった
床に物がなくなったおかげで、コードレスのスティック掃除機1台で家中をスムーズに掃除できるようになり、時短になった。
洗濯が楽になった
洗濯物になる布製品を減らしたことで、洗濯の回数や干す手間がぐっと減り、日常の家事負担が軽減できた。
例)
・敷きパッドとシーツが一体になっているものを使う
・冬の毛布を手放し、布団カバーをモコモコ素材に変更
体調不良時の安心感
家族全員が物の定位置を把握しているので、急な体調不良で動けないときにも、薬や必要なものをすぐに持ってきてもらえるようになった。
子どもと遊ぶスペースができた
余計な家具や物がなくなり、子どもと風船遊びなど思いっきり体を動かして遊べる広々とした空間が確保でき、親子のストレス発散にもつながった。
運動や瞑想に集中できる環境
床や周囲に物がないため、ヨガや宅トレ、瞑想をするときも、すぐに始められて気持ちも集中できるようになった。
片付け時間が短縮した
おもちゃは「5分以内に片付く量」と決めて厳選したことで、子ども自身も片付けがしやすくなり、親の負担も減った。
Q4.物を減らす過程で、「こういう方法にしたらうまくいった」「このルールを取り入れたら無理なく減らせた」「これはなくてもよかった」ということを、具体的に教えてください。
1イン1アウト
新しい物を1つ買うときは、必ず何か1つを手放すルールにすることで、収納スペースが圧迫されず、際限なく物が増えることを防いでいます。
「来客用」をやめた
来客用の布団や食器類など「普段使わない物」を思い切って手放したことで、大きめの収納スペースを一気に空けることができました。
布団など使用頻度の低いものは、必要なときにレンタルを活用するように切り替えました。
食器はほぼ全て1軍にして、家族分しか持たないようにしているので、キッチン収納が最低限でも間に合っています。
来客時に食器が足りなかった経験はないですが、紙コップや紙皿で対応できます。
メルカリを活用
ただ捨てるのではなく、メルカリを使って物を売るようにしています。
不要な物を手放しながら収入にもなるので、「他にも売れるものないかな?」と楽しく前向きに手放せるようになりました。
1年ルール
「1年使わなかったら手放す」と明確に期限を決めることで、「いつか使うかも」といった迷いや先延ばしがなくなり、本当に今の暮らしに必要な物だけが残るようになりました。
ミニマリストの発信を見る
ミニマリストの方々の発信を定期的にチェックすることで、自分自身の固定観念が変わり、「あれもこれも」と便利さだけで物を増やさず、「本当に必要か?」「無くても大丈夫かも」と冷静に考える習慣が身につきました。
Q5.家の中をスッキリ保つためにやっている、物を捨てる・見直しするときのルールを、物別にそれぞれ教えてください。
(例:不要品を捨てる・見直す周期、タイミング、こういう状態になったら捨てるーなど)
キッチン用品
3月と9月に備蓄食品の見直しをしているので、そのタイミングでキッチン用品や食品も一緒にチェック。
月1回以下の使用頻度のアイテムは、収納スペースとのバランスを考えて手放し対象に。
また、代用できる物があれば手放すようにしています(例:泡立て器は味噌マドラーで代用)。
服・靴・バッグ
季節の変わり目に、くたびれた服を処分。
昔は「1シーズン着なかった物」を基準にしていましたが、今はすべて着る服だけを持っているので、「状態の劣化」で判断しています。
ハンガーの本数を決めて、それ以上増えないようにコントロール。
毛玉・破れ・型崩れも処分基準です。
日用品(消耗品)
種類が多くなりすぎないように、代用できるものを考えながら選ぶようにしています。
洗剤なども必要最小限に絞り、在庫の数も決めてストック過多を防止しています。
プリント・紙類
学校・保育園のプリントは、もらったその場で確認し、スマホのメモアプリでスキャンしてから処分。
提出物もすぐに記入して子どものバッグに入れるなど「すぐ処理する」ことを徹底。
PTA関連は任期終了後に処分。保険関係書類は年1回、契約書類が届いたタイミングで見直します。
取扱説明書は家の設備関係だけを残し、家電系は基本的に処分し、必要に応じてネット検索で対応。
子どもの学用品・園グッズ
学期末や年度末に見直し、壊れた物やサイズアウトした物は処分。
ノート類は年度末に前学年のものを処分。
教科書は、小学生時代は「1学年下まで」を目安に保管し、それ以前のものは手放していました。
中学生になってからは受験に備え、すべての学年分を保管する予定です。
娘の時に鉛筆を買いすぎてしまった経験から、息子の文房具は「使い切れる量」だけを購入する予定。
子どもの作品・絵
IKEAのSKUBBボックスに「ここに入るだけ」とルールを決めて収納。
ボックスからあふれたタイミングで、子どもと一緒に仕分けして処分。
年度末に見直すことが多いですが、途中で容量オーバーしたときも都度見直しています。
おもちゃ
誕生日や年末など、新しい物が入ってくる前に見直し、子どもと一緒に「もう遊ばないかな?」と確認して手放しています。
ハッピーセットのおもちゃは専用のボックスを設け、あふれたらマクドナルドの回収ボックスへ。
「5分で片付く量」を目安に、持ちすぎないようにコントロールしています。
その他(家電・ケーブル類など)
・用途がわからないケーブルは1年間保管し、使わなければ処分。
・TVを買い換えてサブスク視聴ができるようになったときに、ブルーレイレコーダーを手放しました。
・「現在の暮らしに合っているか」を基準に判断しています。
・GW、お盆、年末年始などリサイクルショップが混雑する前に、大型家電などの持ち込みを済ませています。
・工具や裁縫セットなども出番が少ないため、年に1回見直し、「この1年使わなかった」「収納場所からあふれた」ときには手放しています。
・紙袋は無印のファイルボックスに入れておき、あふれたら処分しています。
Q6.「もったいない」といった気持ちを払拭し、気持ちよく物を手放すために実践していることがあれば、いくつでも具体的に教えてください。
(例:使える物はリサイクルやフリマに出す、別の用途に使う―など)
メルカリで収入に変える
「もう使わないけれど、誰かにとってはまだ使える物」を、メルカリに出品して手放していました。
ちょっとしたお小遣いにもなるので、気持ちよく手放せるうえに、「ほかに手放せる物ないかな?」という意欲にもつながります。
寄付やリサイクルで「役割を終えさせる」
服やおもちゃなど、状態が良いものはリサイクルショップへ持ち込んだり、必要としている知人に譲ることもあります。
次の誰かに使ってもらえることで「捨てる罪悪感」を減らすことができます。
別の用途を考えない
「別の使い道があるかも」「どこかで使えるかも」「いつか使うかも」と考えると手放せなくなるので、考えないようにしています。
「まずは減らすこと」を優先するためのマイルールです。
「今使ってない方がもったいない」と考える
しまいこんで使っていない物こそ、“今もったいない状態”だと意識を変えるようにしています。
使わずに眠らせておくよりも、誰かの役に立った方が物も喜ぶはず、と思って手放すようにしています。
物は使われるために製造されているので、使ってあげられないなら誰かに譲るという意識でいます。
例えば服を100着持っていても体は1つしかないし、1シーズンで何回その服を着るのかを考えると、
「着ておらずクローゼットに仕舞われている期間の方が長い」
という状態は、せっかく買ったのに着ていないので、それこそもったいない。
1シーズンで何回着るのか?ということも考えてみると、手放しやすくなると思います。
Q7.新しく物を買い足すときのルールがあれば、具体的に教えてください。
(例:タオルなどの日用品は買い替えの周期を決めている、買う前には商品情報をリサーチしてから買う―など)
「買い足し」ではなく「買い替え」でアップデートしていく
何かを買い足すときは、「今ある物を手放す前提」で購入しています。
「買い足し」ではなく「買い替え」にすることで、物が増えすぎるのを防ぎながら、生活の質を少しずつアップデートしています。
収納スペースを確認してから購入
「どこに収納するか?」がすぐにイメージできない物は買いません。
収納場所ありきで考えることで、衝動買いを防げています。
買う前に用途が明確かを確認する
「何に使うかがはっきりしていない物」はなるべく買わないようにしています。
漠然と「便利そう」と思っても、使わないまま終わることが多いと気づいたので、「使う場面」がすぐに想像できる物だけを選ぶようにしています。
「今の暮らしに必要か?」をしっかり見極めています。
リサーチして納得してから買う
高価な物や使用頻度が高くなりそうな物は、レビューや口コミをよく調べてから購入。
家事の負担を減らしてくれるような「助けになる物かどうか」も意識しています。
タオルは6月と12月に買い換え
「梅雨時期(6月)」と「年末(12月)」に買い換えると決めておくことで、「そろそろ替え時?」と悩む時間を減らしています。
毎回同じ種類のタオルを選ぶことで、探す手間や失敗もなく、時短にもつながっています。
以前は無印良品のタオルを使っていましたが、廃盤になったので、現在はスタンダードプロダクトのタオルを購入しています。
Q8.現在残している物(使っている物)の基準やルールがあれば、具体的に教えてください。
「今」の暮らしに合っているかどうか
「今の自分たちの暮らし」に本当に必要かを基準にしています。
過去の生活スタイルや、いつかやるかも…という未来に合わせた物は極力残さないようにしています。
使用頻度が高いかどうか
使用頻度が低いものは、「なくても困らなかった」と思えることが多く、手放す判断もしやすいです。
家事がラクになるものかどうか
掃除や片付けがラクになる物、メンテナンスしやすい物を選ぶようにしています。
見た目だけでなく「使いやすさ」や「管理のしやすさ」も重視しています。
今は子育て中で複数の仕事をしていることもあり、自由な時間が少ないため、時短できるようなものや家事楽につながる物は残しています。
「何でもかんでも減らす」のではなく、ライフスタイルやタイパも判断材料になっています。
自分や家族が「本当に好き」な物だけにする
「気に入っている」「安心感がある」「使っていてストレスがない」と感じられる物だけを残すようにしています。
使い切れる量かどうか
特に日用品や文具などは、「持ちすぎて管理が面倒になるくらいなら、必要な分だけ持つ」が我が家のルールです。
収納場所に無理なく収まっているか
物の定位置が決まっていて、そこに「無理なく収まっていること」を大切にしています。
収納がパンパンになってきたら、それは見直しのサインとして捉えています。
Q9.特に、夏場(7月~9月)に捨てるとスッキリする物、捨てたほうがいい物を具体的に教えてください。
(例:キッチン周りの物、子どもの学用品、プリント類―など)
キッチン周りの食品・グッズの見直し
夏前後(特に防災備蓄の見直しをするタイミング)に、賞味期限切れの備蓄食品や使っていない調味料、古くなった保存容器などを見直しています。
暑さで食品や調味料なども傷みやすいので、このタイミングで見直すようにしています。
保冷剤も「すぐにぬるくなってしまうもの」に気付きやすいので、手放すタイミングにちょうど良いです。
今シーズン使わなかったクーラーボックスは処分対象とし、必要なときに改めて購入する方がスペース的にも合理的です。
夏服・インナーの入れ替え
汗ジミ・色あせ・生地のくたびれた夏服やインナーは、シーズン中でも気づいたときに処分するようにしています。
また、1シーズン着なかった夏服もこのタイミングで見直し、今後も着るかどうかを判断しています。
電車移動などの冷房対策に買ったけど、持ち運びにくい(シワになりやすい)カーディガンなども判断しやすいタイミング。
エアリズムなどの機能性インナーは湿気を吸収しやすいので、劣化の見極めや買い替えにも夏はぴったりのタイミングです。
夏に使わなかった季節アイテムを見直し
プールバッグや水遊びグッズなど、今年の夏に使わなかった物は「来年も使わないかも」と考えて、シーズン終わりに手放すようにしています。
水鉄砲など水遊び系のグッズは、中がしっかり洗えずにカビが発生することもあるため、基本的には1シーズンで手放すようにしています。
毎年100均などでたくさんの種類の水遊びグッズが出るので、新しいものを買うことで子供も新鮮に楽しめるし、衛生面でも安心です。
水遊び用オムツも「来年もまだ使うかも」と残しておきがちですが、機能性が劣る可能性なども考えて1シーズンで使い切るようにしています。
日傘や帽子も「今の自分に合っているか」を確認しやすい時期です。
学用品やプリントの整理
1学期で役目を終えたプリントやノートなどは夏休み中に一度整理。
テストなどは見返すことがないので、手放します。
自由研究や工作などで使った材料の端材なども、このタイミングで処分すると気持ちも空間もスッキリします。
Q10.暑い夏や忙しいときでも、何も考えずに捨てられるコツやルールを具体的に教えてください。
「アウト」と「セーフ」の基準を明確にする
迷うことを減らすために、あらかじめ処分基準を決めておきます。
例えば服なら「動きにくい」「流行遅れ」「スタイルが悪く見える」など、自分なりのアウトリストを作っておき、そこに当てはまるものは考えずに手放すようにしています。
判断がルール化されることで、悩まず行動に移しやすくなります。
暑さでやる気が出ない時こそ、細かく・短時間で
暑い日はまとめて片付けようとせず、「今日はこの引き出しだけ」「今日は1つだけ捨てる」と決めて取り組むようにしています。
小さな達成感が続けるコツです。
ミンスゲームを取り入れてみる
ミンスゲームとは、その日の日付の数だけ物を手放していく方法です。
1日は1個、10日は10個、31日は31個というように進めていくと、31日間で最大496個の物を手放すことができます。
数が明確なので迷いにくく、ゲーム感覚で楽しく取り組めるのが魅力です。
Q11.勝手に捨てにくい家族の物、子どもの物はどうやって管理しているのか教えてください。
子どもの物は一緒に見直す
子どもの作品やおもちゃは勝手に捨てず、一緒に「これはまだ遊ぶ?」「これ好きだった?」と声をかけながら見直すようにしています。
本人の気持ちを尊重しつつ、「ここに入るだけ」とルールを共有することで、納得感のある整理ができます。
「定位置」と「上限」を決める
子どもの物には、それぞれ「このBOXに入る分だけ」など定位置と量のルールを決めています。
「あふれたら見直す」と伝えて、一緒に整理するようにしています。
夫の物は本人に判断を任せる
夫の私物には手を出さず、聞かれたらアドバイスする程度にしています。
または「これは処分していい?」と確認するようにしています。
私が片付ける際も、「不要かな?」と思うものは1箇所にまとめておき、夫に1つずつ見せて確認してから処分するようにしています。
手放したいものの理由を説明する
「なぜ手放したいのか」「手放したらどんな良いことがあるのか」「手放して困ることは何か」の意見を出し合い、家族や夫婦で手放すかどうかを決めています。
家族会議ほどしっかりした形式ではないですが、雑談っぽく会話をするようにしています。
みんなの意見を聞くことで、それぞれ残す理由、手放したい理由を知ることができ、お互いの気持ちを尊重できるようになります。
Q12.片づけや家事をラクにするために、「あえてやめたこと、やらないこと」があれば、具体的に教えてください。
(例:洗濯物はハンガーのまま収納し、たたまない/細かい分類はしない…など)
服をたたまず、ハンガー収納にした
服はすべてハンガーにかけて収納し、「たたむ」作業をやめました。
持っている服の量が一目でわかりやすくなり、衣替えの必要もなくなりました。
管理がラクになっただけでなく、服の見直しのタイミングも自然と増えました。
洗濯物を干すのをやめて、乾燥まで一気に済ませるようにした
洗濯はすべて乾燥機まで済ませるようにしたことで、天気や時間を気にせず家事が回るように。
「干す」「取り込む」手間がなくなり、家事のハードルがぐっと下がりました。
掃除のたびに物をどかすのをやめた
床に物を置かないようにしたことで、掃除機をかける前に「片付ける作業」が不要に。
掃除の頻度も上がり、清潔をキープしやすくなりました。
玄関マットなどの敷物をやめた
玄関やキッチンに敷いていたマット類をすべて撤去。
洗濯の手間が減り、掃除もしやすくなりました。
買い物に行くのをやめて、ネットスーパーに切り替えた
子どもを連れての買い物やレジの待ち時間がストレスだったため、ネットスーパーを活用するように。
自宅で空き時間に注文でき、在庫管理もしやすくなりました。
「あれば便利かも」で置いていた家具をやめた
サイドテーブルや小さな棚など、「あると便利そう」で置いていた家具を思い切ってやめました。
床面積が広くなり、物を置く場所が減ったことで“置きっぱなし”も減り、部屋全体がスッキリしました。
家事時間を測って、やめるべき作業を見極めた
洗濯物をしまうのに3分、トイレ掃除に1分など、家事の所要時間を実際に測るようにしました。
思った以上に時間がかかっている家事が見えると、「この手間を減らすにはどうすればいいか?」を具体的に考えやすくなります。
その結果、干す・たたむといった作業をやめたり、収納方法を変えるなど、ムダを手放す工夫につながっています。
例)バスタオルを畳まず、掛ける収納に
Q13.片づけや断捨離をしても、すぐリバウンドしてしまうという人に対して、アドバイスをお願いします。
スモールステップでOK!最初から完璧を目指さない
「一気に全部きれいにしよう」と思うと疲れてしまって続かないので、「今日は引き出しひとつだけ」など、小さな行動でOKと自分に許可を出すことが大切です。
「物の定位置」より「量の上限」が大事
しまう場所を決めることも大切ですが、そもそも「これ以上増えない仕組み」にしておくことでリバウンドを防げます。
「この引き出しに入る分だけ」「ボックス1つ分だけ」と決めておくと、増えたら見直すタイミングが自然と生まれます。
散らかるのは「収納が悪い」と言うより「物の量」が多いから。
4人乗りの車に8人乗れないように、収納から溢れる=容量オーバーということなので、オーバーしたものを減らすようにしてみることが大事です。
使い勝手を優先した仕組みにする
戻しやすさ、見やすさ、動線に合っているかを意識することで、片付けるのがラクになります。
「散らかるのは性格のせい」ではなく、「仕組みが合っていないだけ」という目線で見直すと気持ちもラクになります。
「一度見直せば終わり」ではなく、暮らしに合わせて見直すのが前提
子どもの成長や生活スタイルの変化に合わせて、持ち物や収納も変わっていきます。
「一度片付けたのにまた散らかる…」ではなく、「暮らしが変化したから、見直すタイミング」と捉えると、リバウンドではなく前向きなアップデートになります。
床の見える面積と金運は比例する
これは私自身が実感していることですが、床が見えている=物が管理されている状態。
視界がスッキリしていると、自然と気持ちやお金の流れも整っていきます。
散らかってきたときは「床が見えてるか?」をチェックするのが、私の片付け基準です。
ここまで読んでくれた方
大変お疲れ様でした!
なんと文字数9400文字以上!
読み終わるまで何分かかったでしょう。
(ごめんね!)
大変だったと思うので、読み返しやすいよう、それぞれの項目に分けて深掘りした記事も投稿できるように頑張りますね!
したっけね〜!
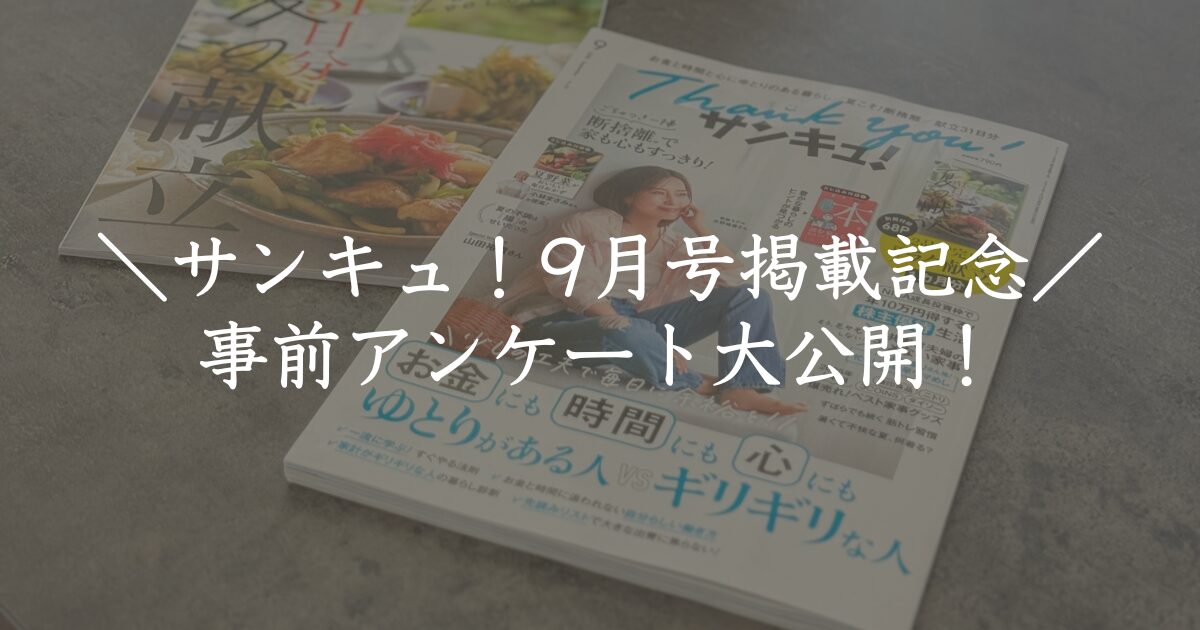

コメント